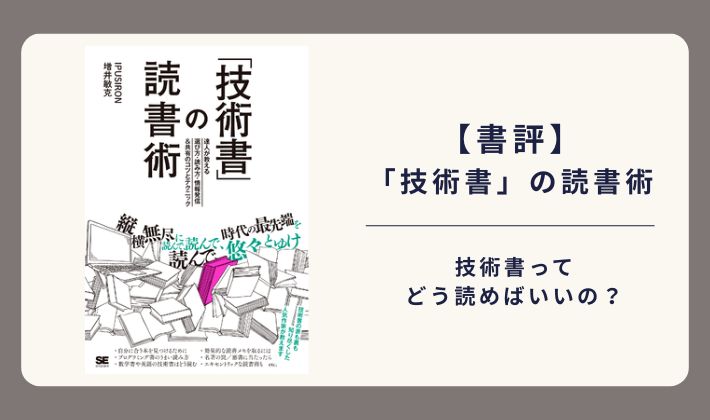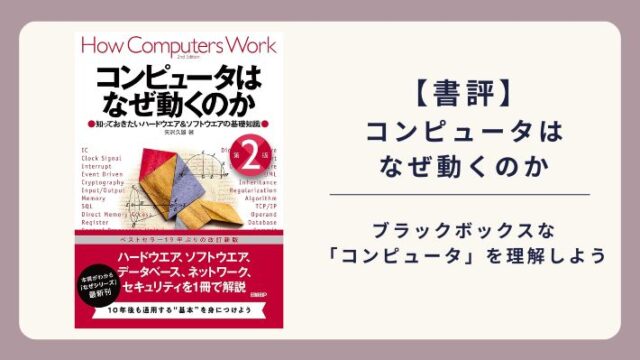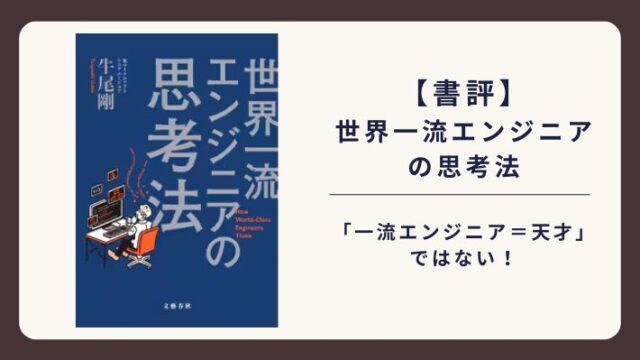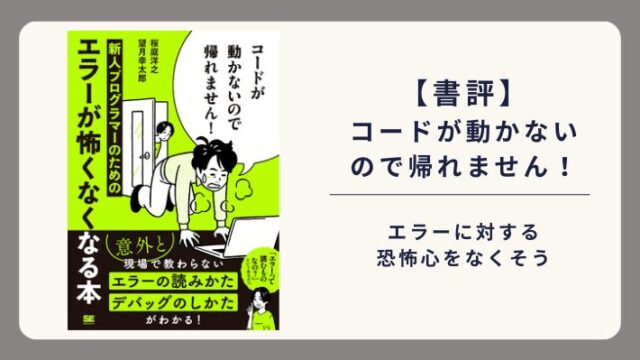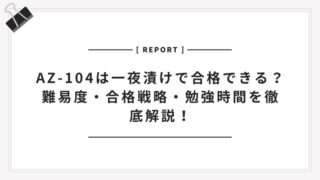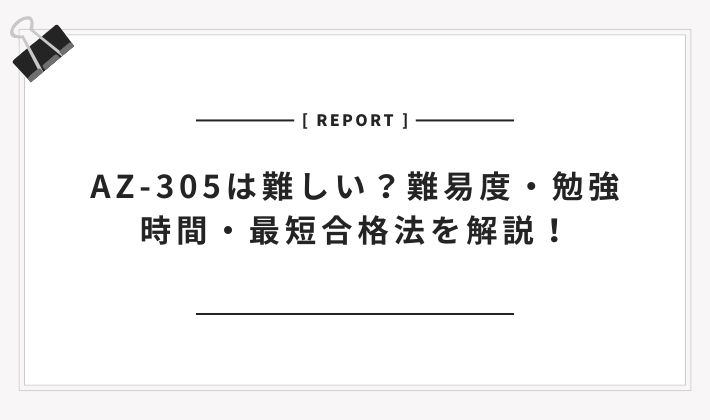はじめに
「技術書ってどう読めばいいの?」
新人エンジニアの私は、そんな悩みをずっと抱えていました。
そんなとき出会ったのが、本書『「技術書」の読書術』。
ただ読むだけでなく、読書法そのものが学べる本書は、まさに技術書初心者の道しるべになる一冊でした。
この記事では、私が特に面白いと感じたポイント6つを中心に、本書の魅力と読後の変化をお届けします。
新人エンジニアの方にはぜひ手に取ってほしい1冊です。
『「技術書」の読書術』ってどんな本?
本書は、数多くの技術書を読み込み、さらに自らも技術書を多数執筆している2人の著者が、技術書の「選び方」「読み方」「情報発信の仕方」の3つの観点から、実践的なノウハウを具体的に紹介してくれる一冊です。
「技術書をどう選べばいいのか?」「どう読めば知識として定着するのか?」「学んだことをどうアウトプットすればいいのか?」
そんな悩みを持つエンジニアに向けて、著者のリアルな体験をもとに、役立つヒントが満載です。
| 書名 | 「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック |
| 著者 | IPUSIRON、増井敏克 |
| 出版社 | 翔泳社 |
| 発売年 | 2022年 |
| ページ数 | 272頁 |
また本書は、「ITエンジニアに読んでほしい!技術書・ビジネス書大賞2024」にて特別賞を受賞。
エンジニア界隈でも注目を集めており、技術書の読み方に悩むすべての人にオススメの1冊です!
https://www.shoeisha.co.jp/press/detail/1106
読書観が変わった!面白かったポイント6選
偶然から学びを得る「くじ引き読書法」
本書の1-2章(著:IPUSIRON氏)では、「くじ引き読書法」というユニークな本の選び方が紹介されています。
この読書法は、適当に選んだ本棚の前に立ち、目をつぶって手に触れた本を最後まで読むというもの。
著者はこの方法のメリットとして、以下のように述べています。
- 知らない分野に触れることで、新鮮な学びと楽しさが得られる
- 他者との差別化や逆転のチャンスにつながる
私自身、読書は好きですが、どうしても読む本のジャンルが偏りがちです。
だからこそ、思いがけない本との出会いがある「くじ引き読書法」は、新たな発見を得るためにも一度試してみたいと感じました!
英語の技術書に対する苦手意識が消えた!
同じく1-2章(著:IPUSIRON氏)では、英語の技術書を読むという選択肢が提案されており、そのメリットも丁寧に解説されています。
- 翻訳される前の技術書を読むことで、最新技術に触れられる
- 洋書でしか発売されていない書籍にアクセスできる
- 翻訳本より安く入手できる
- 原著と翻訳本を読み比べられる
さらに、洋書は難しそうで敬遠しがちですが、著者はその先入観を取り払ってくれます。
実際、私は「技術書なら難しい単語や言い回しも少なく、比較的簡潔な文章であることが多い」「画面のスクリーンショットやプログラムのコードは読み取れる」との言葉に勇気づけられました。
この箇所を読み、私はこれまで英語の技術書に感じていた苦手意識が薄れました。次に技術書を購入する際は、洋書も視野に入れて選びたいと思います!
「いやでも、まだ自分には洋書なんて読めないよ…」と不安に感じているあなたには、著者の至言をお届けします!
洋書のために英語を勉強するのはよいことですが、「英語の勉強が完了してから洋書を読む」と考えてはいけません。なぜなら英語の勉強が完了するときは永遠に訪れないからです。
(84頁より)
同テーマの3冊読みで理解がグッと深まる!
本書2-1章(著:増井敏克氏)では、同じテーマについて「入門書・専門書・逆引き」など、異なる視点の3冊を読む手法が紹介されています。
さらに、入門書だけを3冊読むなど、同じ難易度・内容の本を3冊読むことで、共通点や違いが見えてきて、理解が格段に深まるとも書かれています。
私はこれまで1冊の本で学ぼうとしてしまいがちでしたが、この箇所を読んで、複数の本を読み比べて理解を深めることの重要性に気づかされました。
新人エンジニアとして、技術を深く理解していくためにも、技術書を読み比べていこうと思います!
言語学習のロードマップが明確になった!
同じ2-1章(著:増井敏克氏)では、プログラミング言語の学習についても、段階的な戦略が示されています。
- まず1つめの言語で仕事に役立つレベルのものを作れるようになる。
- 次は1つめと近い種類の言語を学習する。
- その後、型やパラダイムの異なる言語へ挑戦する(例:コンパイル型⇔インタプリタ型、オブジェクト指向型⇔関数型)
私はこれまで「次に何を学べばいいんだろう…」と迷っていましたが、この指針のおかげで今後の学習計画がぐっと立てやすくなりました。
今はRubyとPHPを学習しているため、これらを実務レベルまで磨いたら、次はコンパイル型の言語にも挑戦してみようと思います!
一点突破読書法で“オンリーワン”を目指す
本書2-2章(著:IPUSIRON氏)では、特定分野の本を徹底的に読む「一点突破読書法」が紹介されています。上述の「同テーマ3冊読み」と似た手法ではありますが、この方法は非常にストイックで、
- 最低でも同一分野の本を20冊以上読む
- 可能であれば入手できる国内外の全書籍を読む
- 3年かけて3分野を習得し、自分だけの強みをつくる
というように、量と継続がカギとなる読書術です。
ナンバーワンにはなれなくても、分野の組み合わせ次第で“オンリーワン”になれる──この考え方は、私のような新人エンジニアにも大きな勇気を与えてくれました。
まずは実務スキルの習得から始め、将来的には自分の強みを持ったエンジニアになれるよう努力していきます!
「情報発信=価値創出」に背中を押された
本書3-1章(著:増井敏克氏)では、ブログやLT会などでのアウトプットの重要性が語られています。特に心に残ったのは次の2点です。
- 初心者ならではの視点や気づきが、他の学習者の役に立つ
- 出版当時から情報が変化している分、最新情報の発信にも価値がある
正直、「新人の自分が発信しても意味があるのかな…」と思っていた時期もありました。
でも今は、だからこそ誰かの役に立てるかもしれないと考え、こうしてブログで発信を続けています。
この本が特に刺さる人・オススメの読者像
この本を特にオススメしたいのは、次のような方々です!
- 技術書に苦手意識がある新人エンジニア
- 「効率よく、なるべく近道で学びたい」と考えがちな人
それぞれ、詳細を以下に説明していきます。
技術書に苦手意識がある新人エンジニア
私自身もそうでしたが、「技術書ってどう選ぶの?」「どこから学べばいいの?」と迷いがちな新人エンジニアにこそ、この本はぴったりです!
本書では、熟練エンジニアである著者お二人が実践してきた「技術書との付き合い方」を丁寧に解説してくれています。
選び方、読み方、活かし方、さらには情報発信の仕方まで網羅されていて、とても参考になります。
読み終えたときには、自分なりの学習プランを立てたくなっているはずです!
「効率よく、なるべく近道で学びたい」と考えがちな人
今の時代、「いかにコスパよく学ぶか」が重視されがちです。でも、この本を読んで一番感じたのは──
著者たちの“技術書が大好き!”という気持ちと、“学ぶことそのものを楽しんでいる姿勢”でした。
たとえば、前述の「くじ引き読書法」で未知の分野に挑戦してみたり、1つのテーマをとことん掘り下げて読む「一点突破読書法」など、遠回りに見えて実は本質的な学び方が紹介されています。
「最短距離」や「効率」ばかりを追い求めてしまう人にとって、この本は価値観を揺さぶる一冊になるかもしれません。
多くの本に触れて、自分のペースで楽しみながら学ぶ──そんな学び方の大切さに気づけるはずです!
逆にこの本が合わないかもしれない人
一方で、この本があまり刺さらないかもしれないのは、既に「多読」や「アウトプット」が習慣化されている中~上級エンジニアの方です。
というのも、本書のメインテーマは「技術書の選び方・読み方・活かし方」といった初〜中級者向けの内容で構成されているからです。
そのため、日頃からすでに実践している方にとっては、「新しい発見が少ない」と感じるかもしれません。
とはいえ、「他の人のやり方も知りたい!」「自分の学び方と比較してみたい!」という目的であれば、十分楽しめると思います。
まとめ
『「技術書」の読書術』は、「読書して満足」で終わりがちだった私に、「読んだあと、どう活かすか?」を教えてくれた一冊でした。
本書を通じて、技術書に対する苦手意識がグッと減り、これからの学習にも前向きになれました。
特に、新人エンジニアの方や、技術書に苦手意識がある方には強くオススメします!
きっとこの本から、「学ぶ楽しさ」と「成長のヒント」が見つかるはずです。